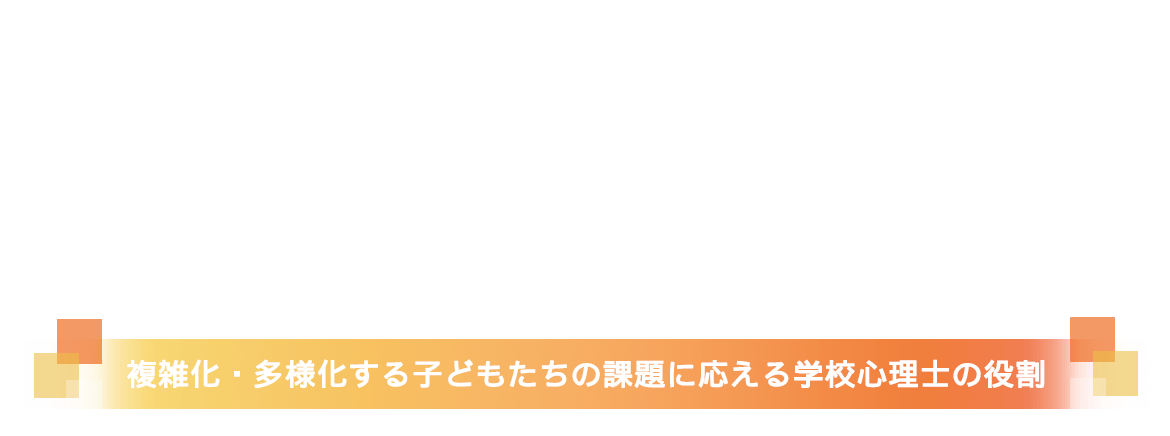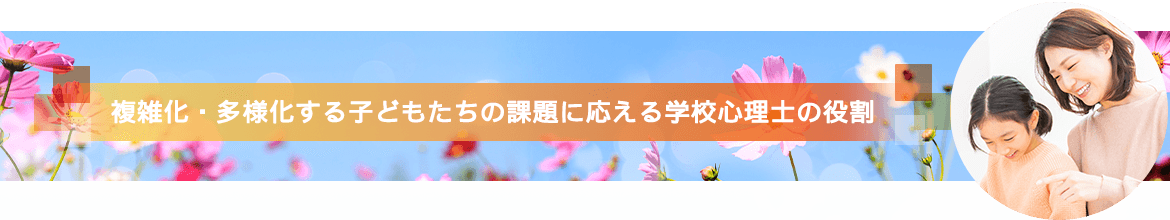各研修講座詳細は【概要】をクリックすると表示されます。
また,各研修講座は2時間ずつとなります。
(時間が長いため,オンデマンド配信ページ上では,講座動画は数本ずつに分かれて掲載となります)
研修①
- 【領域】
- 学校心理学
- 【テーマ】
- 援助要請を支えるスクールカウンセリング
- 【講師】
- 本田 真大(北海道教育大学)
学校では日々の支援の中で支援ニーズがあっても自ら相談(援助要請)しない子どもたちと出会います。本研修では学校生活の質向上をめざす学校心理学の実践家として,特に子どもの援助要請を支える方法を解説します。最初に学校心理学と生徒指導提要のチーム支援に関する基本的知識を確認し,援助要請の困難さと重要性を共有した上で,一次的援助サービス(SOSの出し方教育),二次的・三次的援助サービス(自ら相談しない事例のアセスメントと支援)を解説します。動画を見ながら各自で取り組む演習を交える予定です。
研修②
- 【領域】
- 教授・学習
- 【テーマ】
- 学習者の学習方略について考える
- 【講師】
- 﨑濱 秀行(阪南大学)
学習方略や学習方略に関連することがらは過去の大会の研修でも取り上げられた重要なテーマの一つです。主体的・対話的で深い学びの実現に向けては,学習者(主に児童・生徒)自身が自らの学習方略等の様相をとらえることが必要不可欠でしょう。しかしながら,学習活動に困難を抱えている学習者の場合,自身の学習方略等を客観的にとらえるのが困難なこともあると思います。このような学習者への支援を行う際,まずは支援者として当該学習者の学習方略等の様相をとらえる必要があると思いますが,その際どのようなことに留意しておくと良いでしょうか。本研修では学習者や学校教員がとらえる学習方略等に関する知見に触れつつ,この点について考えてみたいと思います。
研修③
- 【領域】
- 発達心理学
- 【テーマ】
- 子どもの「経験」と社会性の発達
- 【講師】
- 髙橋 淳一郎(城西国際大学)
幼稚園教育要領や保育所保育指針等では「遊びによる総合的な指導」によって子どもの小学校以降の学びの基礎を作ることが謳われている。その一方で保育の現場では「〇〇教室」といった自由な遊びではないプログラムが多く見られるようになった。また,学校現場では新型コロナ感染が落ち着き,コロナ禍では見送られてきた様々な行事や活動が復活してきているが,子どもたちはそれらの行事等を経験することができなかった時期を抱えることとなった。これらが子どもたちの社会性の発達にどう影響しているのか検証するとともに,学校等の現場における集団的な心理教育の可能性について考えていきたい。
研修④
- 【領域】
- 臨床心理学
- 【テーマ】
- 多様な性を生きる児童生徒の理解と支援
- 【講師】
- 葛西 真記子(鳴門教育大学)
近年,LGBTQ+の方々に関する社会の認知は進み,学校教育でも取り上げるべきとの意見が多いが,実際の対応は十分とは言えない状況である。いじめや不登校を経験する性的マイノリティの児童生徒は多く,性別違和感を訴える児童生徒への対応を経験したことのある教員も少しではあるが増加しているが,同性愛や両性愛の児童生徒へ対応したことがある教員は少なく,孤立や不安を抱えやすい状況であることが推測できる。学校心理士として,学校全体の支援体制づくりに関わることで,偏見や差別のない環境を整えることが求められる。すべての児童生徒が尊重され,安全に過ごせる学校を実現するには,学校心理士としてどのような支援ができるかを考える。
研修⑤
- 【領域】
- アセスメント
- 【テーマ】
- 「戦略」のための心理教育的アセスメント
~基礎から仮説の生成とコンサルテーションへ~ - 【講師】
- 芳川 玲子(星槎大学)
学校心理士が行う心理教育的アセスメントの最終的な目的は,一人ひとりに最適化された支援計画を立案し,具体的な援助へとつなげることです。本研修では,①心理アセスメントの意義,目的,基本的なプロセスの理解。②主要な心理検査の選択,実施,解釈のポイントの習得。③複雑なケースの仮説の生成。④個別最適化された支援計画の立案。⑤チーム会議における運用を目標とします。ご一緒に,「戦略」のための心理教育的アセスメントについて考えてみませんか?
研修⑥
- 【領域】
- カウンセリング
- 【テーマ】
- 認知行動療法でとらえる学校での心理支援―実践とエビデンスをつなぐ学校心理士の役割
- 【講師】
- 新井 雅(跡見学園女子大学)
本研修では,学校における心理支援を認知行動療法(Cognitive Behavioral Therapy:CBT)の視点からとらえ,実践とエビデンスをつなぐ学校心理士の役割について学びます。CBTは,子どもたちが抱えるさまざまな問題の改善や予防に寄与するエビデンスを有しており,より良い教育や支援を通じて子どもの成長・発達を促すという,学校教育の基本理念とも合致するアプローチです。また,CBTは個別支援にとどまらず,コンサルテーション,予防教育,多職種連携など多様な局面で活用することができ,学校心理学の理論や支援の枠組みとも高い親和性を持っています。本講座では,学校心理士がCBTの視点や枠組みをどのように活用できるかを整理し,学校での心理支援をCBTの観点からとらえ直すことで,複雑化・多様化する子どもたちの課題に向き合うための実践の幅を広げるきっかけとなることを目指します。
研修⑦
- 【領域】
- 特別支援
- 【テーマ】
- 障害の多様化・複雑化に対応する支援のあり方
- 【講師】
- 大塚 美奈子(上田短期大学)
保育・教育現場では,発達障害を中心とした要配慮児への対応が必須となっています。しかし,障害は多様化,複雑化しており,子どもに合った対応には的確なアセスメントや専門性が必要なケースも増えています。その結果,現場と専門家の連携が不可欠となってきています。この研修では,学習面と行動面の観点からLD等通級指導教室での実践事例を基に支援方法を紹介します学習面では斜視幼児のフロスティッグ視知覚検査から書字へつなげる支援,行動面ではADHD児の「ものを盗る行為」への機能的アセスメントによる支援について,いずれも幼稚園や通常学級との連携を重視した事例を基に情報提供したいと思います。
研修⑧
- 【領域】
- 生徒指導等
- 【テーマ】
- ポジティブ行動支援による学校・学級づくり
〜問題行動を予防して子どもの主体性を育てる〜 - 【講師】
- 大対 香奈子(近畿大学)
児童生徒の問題行動に対しては,注意や叱責,厳しいルールによる管理,監視の強化といった対応が増える傾向があるが,このような対応は問題行動が適切な行動に置き換わるという意味での教育的効果は見込めない。また生徒指導提要の改訂からもわかるように問題が起こってからの事後対応ではなく,予防的・発達支持的な対応が昨今では推奨されるようになってきた。そのような社会的動向の中で最近注目されているのがポジティブ行動支援(Positive Behavior Support; PBS)である。本研修では,PBSの理論的基盤である応用行動分析学による行動理解の仕方を解説し,PBSによる学校・学級づくりの具体的な実践の方法について,実践事例も紹介しながら解説をする。
SV研修①
- 【領域】
- SV研修Ⅰ
- 【テーマ】
- 法と倫理に従った,紛争の未然防止
- 【講師】
- 増田 翔(岩本・佐藤法律事務所)
法律は罰則という強制力をもって実現される一方で,倫理は個々人の行動規範や目標として機能し,倫理に抵触すること自体には,国家権力としての罰則は科されません。一方で,倫理への抵触であっても,所属する組織において規範として明文化されている場合には,強制力が発生し処分を受ける可能性があります。また,倫理的な行動規範への抵触により,法的な問題に発展する可能性もあります。紛争の未然防止の観点から,学校心理士倫理綱領や教員に求められる倫理に基づき,専門職として求められる対応を検討します。また,いじめ防止に関連する法規等を踏まえ,いじめ対応における注意点について確認します。
SV研修②
- 【領域】
- SV研修II
- 【テーマ】
- 学校心理士SVによる教職員へのコンサルテーション・コーディネーション
- 【講師】
- 家近 早苗(東京福祉大学)
学校でのコンサルテーションは,学校という組織や教職員の特徴を理解し,限られた時間の中で,教職員が自ら子どもへの援助に参加し,役割を果たせるように成長することを目指します。そこで,教職員へのコンサルテーションについて,個別の教師に対するコンサルテーション,学校組織に対するコンサルテーションのそれぞれの視点から,学校心理士スーパーバイザーとして行うコンサルテーションのポイントについて考えていきたいと思います。また,コンサルテーションと関連する学校でできるアセスメントの方法について検討し,コンサルテーション・コーディネーションの具体的な実践について紹介したいと思います。
SV研修③
- 【領域】
- SV研修III
- 【テーマ】
- 授業研究と学習評価における学校心理士の実践的関与
―教授・学習心理学の視点から― - 【講師】
- 梶井 芳明(東京学芸大学)
学校現場では,教員の授業力向上と組織的な学びを促進するために,授業研究が広く行われています。また,学習評価は,学習者の意欲や自己効力感,学びの質に影響を及ぼす重要な営みです。本研修では,教授・学習心理学の知見をもとに,授業研究や学習評価に学校心理士がどのように実践的に関与できるのかを検討します。児童生徒理解に基づく観察視点,省察を支える対話の設計,教員間の心理的安全性の保障など,学校心理士が教育実践の改善に貢献しうる役割について,理論と事例の両面から考えていきます。
准士研修
- 【領域】
- 准学校心理士研修
- 【テーマ】
- 発達障害の基礎的理解と保護者対応
- 【講師】
- 岩澤 一美(星槎大学)
令和4年に文部科学省が行った「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査」によると,通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒の割合は,平均して8.8%となっています。学年別にみると小学校1年生の児童では,12.0%となっており,就学にあたって達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする幼児は,支援級に在籍することも考えられることから,幼稚園・保育園・こども園では,さらに大きな割合になると予想されます。こうしたことをふまえ,発達障害について理解を深めるとともに,そうした特性を持つ子どもの保護者への対応について,具体的に解説します。