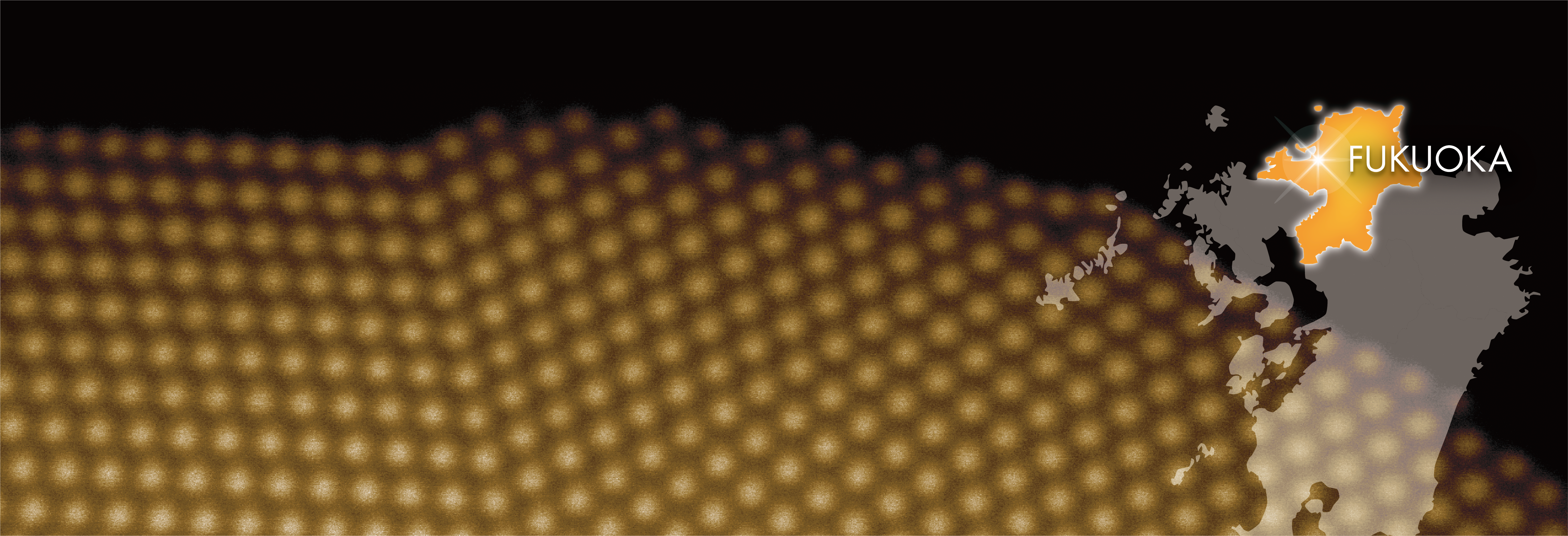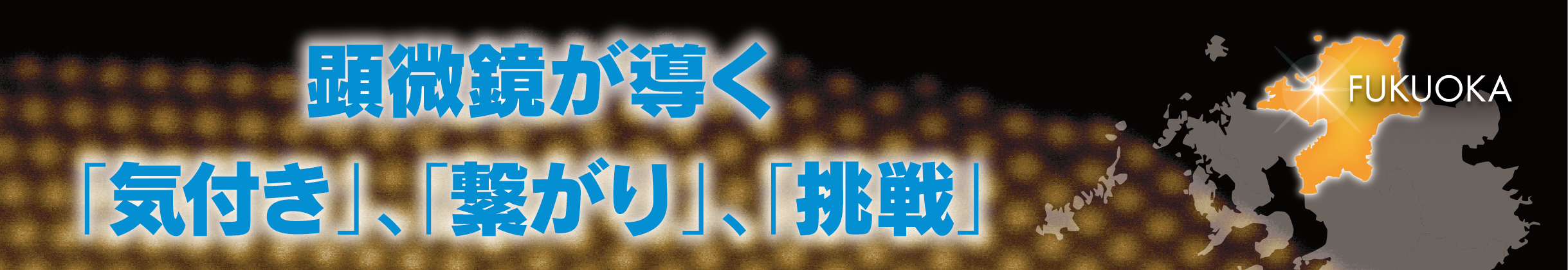シンポジウムセッション 概要・招待講演者
S-1 国際若手サテライトシンポジウム
国際若手シンポジウムでは、最先端の顕微鏡技術を駆使する世界的な若手研究者による講演、また若手研究者に向けた教育講演を行う。このシンポジウムは、大学院生や学部学生など次世代の研究者の育成も推進しており、世界的に進められている最新の顕微鏡技術を学ぶ機会を提供するため、毎年開催される顕微鏡学会の期間において、無料かつハイブリッド形式で開催している。多様な顕微鏡技術についてその原理と発展の経緯を学び、材料系と生物系の双方で活用される顕微鏡技術について学際的な交流を促進する場となることを目指す。
【講演予定者】
- Rafal E. Dunin-Borkowski (Ernst Ruska Center, Germany, Keynote speaker)
- Jungwon Park (Soul National University, South Korea)
- Roger Guzman (Institute of Materials Science of Barcelona, Spain)
- Luiz Tizei (CNRS, France)
- Toshiaki Tanigaki (Hitachi, Japan)
- Yu Toyoshima (The University of Tokyo, Japan)
- Wang Kai (Chinese Academy of Sciences, China)
- Mao Oide (The University of Osaka, Japan)
- Victoria Trinkaus (Max Planck Institute of Molecular Physiology, Germany)
ほか調整中
【発表構成】
招待講演のみ
【セッション企画者】
麻生亮太郎(九州大学)、石川亮(東京大学)、柏木有太郎(東京大学)
【開催日】
2025年6月8日 (日) 12:30-18:20
【開催地】
福岡国際会議場
【開催形式】
現地参加およびオンライン参加
【参加費】
無料(第81回学術講演会とは独立に実施するので、日本顕微鏡学会会員・非会員を問わず無料です。)
【申込方法】
第81回学術講演会の演題申込みとは別に行います。下記申込フォームよりお申込みください。
参加申込締切:2025年6月7日(土)
S-3 量子ビーム顕微イメージングの進展
長年にわたりナノスケールの物質構造イメージングは、高輝度の電子銃と電磁石レンズによる軌道制御技術を有する電子顕微鏡の独壇場であったが、近年の装置開発や実験技術革新、解析手法の多様化・高度化に伴い、X線、中性子、ミューオン等を用いた顕微イメージングにも進展がもたらされ、各線種に特徴づけられた構造情報が得られる状況となっている。本シンポジウムでは、それぞれの最新の性能とアプリケーションの紹介を通じて、得られる構造情報の扱いの議論や、横断・複合利用も含めた今後の幅広い顕微イメージングについての期待と可能性を討論する。
【キーワード】
放射光、X線、中性子、ミューオン、量子ビーム
【講演予定者】
- 亀島敬(高輝度光科学研究センター)
- 広視野・高解像度X線画像検出器DIFRASの開発(仮)
- 井上陽登(名古屋大学)
- 超高精度ミラーによる放射光X線の高度利用(仮)
- 竹内晃久(高輝度光科学研究センター)
- 放射光x線マルチスケールCTによる非破壊3次元階層構造イメージング(仮)
- 永谷幸則(高エネルギー加速器研究機構)
- 透過型および走査型ミュオン顕微鏡の開発(仮)
- 宍戸寛明(大阪公立大学)
- 超伝導中性子検出器によるエネルギー分解中性子イメージング(仮)
- 木村隆志(東京大学)
- SPring-8/SACLAでの軟X線アクロマティック光学系を利用した顕微分光イメージング技術の開発(仮)
【発表構成】
一般講演、招待講演
【セッション企画者】
杉山武晴(九大シンクロトロン光利用研究センター、放射光担当)、高橋幸生(東北大学、放射光担当)、矢代航(東北大学、X線担当)、永谷幸則(KEK-PF、ミューオン担当)、篠原武尚(原子力機構、中性子担当)
【担当プログラム委員】
山﨑順(大阪大学)